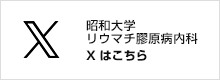Inebilizumab for Treatment of IgG4-Related Disease
J.H. Stone, A Khosroshahi, W. Zhang, E. Della Torre, K. Okazaki, Y. Tanaka, J.M. Löhr, N. Schleinitz, L. Dong, H. Umehara, M. Lanzillotta, Z.S. Wallace, M. Ebbo, G.J. Webster, F. Martinez Valle, M.K. Nayar, C.A. Perugino, V. Rebours, X. Dong, Y. Wu, Q. Li, N. Rampal, D. Cimbora, E.L. Culver, for the MITIGATE Trial Investigators*
Division of Rheumatology, Allergy, and Immunology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Rheumatology Clinic, Massachusetts, USA.
N Engl J Med 2025;392:1168-77.
——————————————————-
<サマリー>
IgG4関連疾患に対するCD19をターゲットとするinebilizumabの有効性を検証するPhase3のRCT。135名が登録され、inebilizumab群では疾患再燃のリスクが有意に低く(10% vs 60%、HR 0.13)、年間再燃率や治療・ステロイド不要の完全寛解率も有意に改善。一方、重篤な有害事象はinebilizumab群でやや多かった。
——————————————————-
<背景>
・IgG4関連疾患は、CD19陽性B細胞が豊富に含んだ腫瘤性病変の形成を特徴とし、これらのB細胞はサイトカインを介して直接、あるいはT細胞の活性化を介して間接的に、炎症や線維化を誘発
・本疾患の病態生理には、抗原依存的なB細胞サブセットとCD4陽性およびCD8陽性Tリンパ球との相互作用が関与し、組織障害や線維化を促進
・inebilizumabはCD19をターゲットとした抗体製剤で、日本ではNMOSDに使用されている
・リツキシマブの効果は、ケースレポートやオープンラベルRCTにて示されているのみ
・本研究では、GC+inebilizumabとGCののみ群にによる治療法の安全性と有効性を比較
<研究デザインの型>
・多施設、二重盲検RCT
・22カ国の80施設で実施
・参加者は、初発または再発の疾患かどうかで層別化
・inebilizumab群またはプラセボ群に1:1の比率で無作為に割り付け
・ランダム化は音声応答システムまたはWeb応答システムを用いて実施
<Population、およびその定義>
・初発および再燃したIgG4関連疾患
・年齢18歳以上
・2019年ACR/EULARのIgG4関連疾患分類基準を満たす
・少なくとも2つの臓器に病変を有する
・再燃に対しグルココルチコイド治療の開始または継続が必要
<主な介入およびコントロール、および、その定義>
・Inebilizumab300 mgまたはプラセボを、1日目、15日目、26週目に点滴静注
・全参加者は無作為化前に3〜8週間のGC治療
・ランダム化の前日にはPSL20mgまで減量
・前投薬(mPSL100 mg、抗ヒスタミン薬、解熱剤)
・PSLは2週間ごとに5 mgずつ漸減され、8週間で中止
・再燃時のグルココルチコイド使用は許容
<主なアウトカム、および、その定義>
・主要アウトカム
・最初の治療を要した再燃とし、イベント発生までの時間
・再燃は、中央の判定委員会で判断
・再燃の定義:IgG4RDに特有の臓器別再燃基準を満たす新規または増悪した臨床所見があり、他の疾患が否定
・主な副次アウトカム
・年間再燃率
・第52週時点の再燃なし・治療なしの完全寛解率
・第52週時点の再燃なし・GCなしの完全寛解率
※完全寛解の定義:再燃がない、再燃に対する治療がない、IgG4-Related Disease Responder Indexが0または研究者による疾患活動性の臨床的にない
・安全性:有害事象、および臨床検査値の変化
<解析方法>
・サンプルサイズ計算:再燃リスクを65%低下させる効果と見積もり、β 90%、α 0.05から計算
・メインアウトカム解析:Cox比例ハザードモデル、説明変数:治療、層別化因子
・ランダム化を受けいずれかの治療を1回以上投与されたfull analysis set(ITT原則)
・フレアのない寛解:ロジスティック回帰モデル
・年間再燃発生率:負の二項回帰モデル
<結果>
・135名が無作為化され、Inebilizumab群に68名、プラセボ群に67名が割付
・127名(94.1%)が52週の治療期間を完遂
・再燃発生までの期間:プラセボと比較して87%低下(HR:0.13、95%CI:0.06~0.28、P<0.001)
・再燃:Inebilizumab群では7名(10%)、プラセボ群では40名(60%)
・再発年間発生率は、Inebilizumabにより86%低下(HR:0.10、95% CI:0.05~0.21)。プラセボ群のハザード比は0.71(95% CI:0.53~0.94)・・・群間の発生率比0.14(95% CI:0.06~0.31、P<0.001)
・再燃なし・治療なしの完全寛解率:Inebilizumab群57%(39名)、プラセボ群22%(15名)(OR:4.68、95% CI:2.21~9.91、P<0.001)
・再燃なし・GCなしの完全寛解:Inebilizumab群59%(40名)、プラセボ群22%(15名)と高かった(OR:4.96、95% CI:2.34~10.52、P<0.001)
・治療期間中の平均GC総量:Inebilizumab群118.3 mg(PSL換算)、プラセボ群1384.5 mg(最小二乗平均差 −1264.2 mg(95% CI:−1689.2~−839.2))
・GC治療を完全に中止:Inebilizumab群61名(90%)、プラセボ群25名(37%)
・安全性
・1回以上の有害事象:Inebilizumab群66名(97%)、プラセボ群66名(98%)
・グレード3以上の有害事象:Inebilizumab群12名(18%)、プラセボ群8名(12%)
・重篤な有害事象:Inebilizumab群12名(18%)、プラセボ群6名(9%)で発生し、複数の対象者に共通するものなし
<Limitation>
・規模が比較的小さく、より大規模な集団にInebilizumabを投与した場合の安全性および有効性は不明確。しかしながら、他疾患でのInebilizumab使用実績を参照にすることで代用は可能
・IgG4関連疾患に対する以前の治療歴を有する参加者は少数
・試験全体の疾患罹病期間の中央値は比較的短い
・ランダム化後の一部のベースライン特性に群間の不均衡
・単一臓器病変のみを有する患者が除外。しかしながら、複数の大規模コホート研究において、IgG4関連疾患では多臓器罹患が一般的であり、罹患臓器数の中央値は2~4臓器以上である
・RCT全般にいえることだが、効果検証を主目的としたサンプルサイズ設計であり、安全性評価が過小評価される
<研究の強み>
・B細胞をターゲットした治療の初のRCTである
<メカニズム>
・CD19陽性B細胞が豊富に含んだ腫瘤性病変の形成を特徴とし、これらのB細胞はサイトカインを介して直接、あるいはT細胞の活性化を介して間接的に、炎症や線維化を誘発しており、このCD19をターゲットした。
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・NMOSDですでに使用されており、安全性の情報の蓄積がすでにあることは安心材料。28週間の治療期間中における感染症の発生率はInebilizumab群とプラセボ群で同程度であり、Inebilizumab群で報告された感染症の大部分は軽度。さらに、4年間のオープンラベル期間においても感染症の発生率は増加なし。
・52週までのデータであり長期のデータが必要(現在3年間のopenラベル試験実施中)
・100mgあたり350万円の薬価であり、今回の試験で使用した300mgであると約1000万円となり費用対効果を考えねばならない
文責:矢嶋宣幸