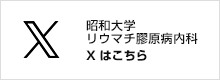Real-Life use of the PEXIVAS reduced-dose glucocorticoid regimen in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis
PEXIVAS試験の減量ステロイドレジメの実臨床での検討
Sophie Nagle, Yann Nguyen, Mary-Jane Guerry, Thomas Quemeneur, Dimitri Titeca-Beauport, Thomas Crépin, Rafik Mesbah, Idris Boudhabhay, Grégory Pugnet, Céline Lebas, Antoine Néel, Alexandre Karras, Eric Hachulla, Juliette Woessner, Vincent Pestre, Raphaël Borie, Stephane Vinzio, Jean-Baptiste Gouin, Sara Melboucy-Belkhir, Roderau Outh, Benjamin Subran, Mathieu Gerfaud-Valentin, Sebastien Humbert, Philippe Kerschen, Yurdagul Uzunhan, Tiphaine Goulenok, Maxime Beydon, Nathalie Costedoat-Chalumeau, Xavier Puechal, Benjamin Terrier
Intensive Care Unit, Avicenne Hospital, APHP, Bobigny, France
Ann Rheum Dis. 2025 Feb;84(2):319-328.
——————————————————-
<サマリー>
ANCA関連血管炎患者234名を対象に、PEXIVAS試験の減量GCと標準GCを比較した多施設後ろ向き研究。減量GCは主要複合評価項目(死亡、ESKD、寛解前進行、再発)の発生と関連し、特にRTX導入例およびクレアチニン高値群で顕著。
——————————————————-
P:重症AAV患者
E:減量GC治療
C:標準GC治療
O:複合アウトカム(再発、寛解前進行、ESKD、死亡)
<背景>
PEXIVS試験:
・AAVに対する寛解導入として標準GCと低用量GCの比較
・低用量GCは死亡、ESKDに関して標準と比べ非劣勢である
・1年後の重篤な感染症は低用量GCで有意に低い
・問題点:
初期の病勢進行や再発は評価されていない
CY導入が多く、RTX導入が少ない
(RTX導入のケースのみでは死亡、ESKDともに標準GCが勝る傾向)
<研究デザイン>
・後ろ向き研究
<セッティング>
・フランス+ルクセンブルクの19施設
・2018‐2022年
<population、およびその定義>
・15歳以上の新規・再発したGPAもしくはMPA(2022 ACR/EULER criteria)
・フランスのガイドラインで重症と定義されCYもしくはRTX導入を要する患者
・除外:GPA/MPA以外の血管炎、RTXとCYC両方の使用歴、redGC以下のGC累積投与量、特定レジメンに従わないGC治療、GC治療データが不十分、アバコパン併用例
・治療開始日が2022.5.6以前(少なくとも追跡期間が6ヶ月以上)
<主な曝露およびコントロール>
・PEXIVAS試験もしくはCORTAGE試験に沿った減量GC(redGC)もしくは標準GC治療(standGC)を実施
・redGC群:PEXIVAS試験と同様(体重50-75kgでは30mg/日で開始、4ヶ月で5mgまで漸減)
・standGC群:以下のいずれかに該当
PEXIVAS試験における標準用量レジメン(体重50-75kgでは60mg/日で投与開始、6か月で5mg/日まで漸減)
CORTAGE試験における標準用量(体重60kgの場合:プレドニゾン60 mg/日で開始、3か月時点で20 mg/日、12か月時点で9 mg/日、18か月で4 mg/日、24か月で中止)
PEXIVAS試験以前にフランスのガイドラインで推奨されていたレジメン(開始時にプレドニゾン1 mg/kg/日、3か月時点で15–20 mg/日、6か月で10 mg/日、12か月で5 mg/日まで漸減)
<アウトカム、および、その定義>
・primary:12カ月以内に発生した複合アウトカム(軽微な再発、重度な再発、寛解達成前の進行、ESKD)
・secondary outcome:12カ月以内に発生した死亡 or ESKD (PEXIVA試験の主要アウトカム)、寛解前進行、再発、寛解達成、重篤感染
<統計解析>
・GCレジメンと主要複合アウトカムとの関連を生存分析により評価
・潜在的交絡因子で調整した重み付けなしの単変量および多変量Cox比例ハザードモデルを用いて関連を評価
・治療群間のベースライン特性の違いに対し、治療重み付けの逆確率(IPTW)法を適用
・傾向スコアは、ロジスティック回帰を用いて計算され、モデルには以下の共変量が含まれた: 性別、年齢、AAVサブタイプ(GPAまたはMPA)、再発性疾患、全身症状、関節および/または筋病変、皮膚、耳鼻咽喉科(ENT)、肺、消化器、末梢神経系、中枢神経系、または心病変、クレアチニン値>300μmol/L(3.39mg/dL)、肺結節、眼窩腫瘤、声門下狭窄、導入治療、血漿交換、BVAS、Five Factor Score(FFS)、およびステロイドパルス。
・IPTWがどの程度治療群を調整させたかを評価するため、重み付けの前後で群間の標準化差を計算。標準化された差が10%未満であればバランスがとれているとみなされ、傾向スコアの算出に使用。その後、Cox比例ハザードモデルを用いて、重み付けされた偽集団におけるGCレジメンと各アウトカムとの関連を評価
・導入療法としてRTXを受けた患者において、事前に規定したサブグループ解析を実施
<結果>
・234人の重症GPAまたはMPA患者が含まれ、108名が標準用量GC(standGC)を、126名がPEXIVAS試験に準拠した低用量GC(redGC)
ベースラインデータ
・中央値追跡期間は25か月
・患者の平均年齢は61歳で、女性は約半数
・GPA 60%、MPA 40%。MPO-ANCAとPR3-ANCAの比率はほぼ同等
・BVAS平均17
・再発症例は25%
・腎障害は70%、平均Cr値232 µmol/L、25.2%(59人)は300 µmol/L超
・導入療法はRTXが71%、CYCが29%。
・GC累積投与量は、6か月時点でstandGC群 4646 mg(IQR: 3966–5381)、redGC群 2520 mg(IQR: 2235–2895)と有意(p<0.001)。
・主要複合評価項目(死亡、ESKD、寛解前進行、再発):
発生:234人中62人(26.5%):standGC群 18.5%(20/108人)、redGC群 33.3%(42/126人)(p=0.01)。
内訳:寛解前の進行:23人(うちredGC群 17人)、軽度再発:11人(うちredGC群 7人)、重度再発:5人(うちredGC群 1人)、ESKD:12人(うちredGC群 8人)、死亡:11人(うちredGC群 9人)
未補正:HR 1.99(95%CI: 1.17–3.38, p=0.012)
多変量補正後:HR 2.20(95%CI: 1.23–3.94, p=0.008)
IPTW補正後:HR 2.03(95%CI: 1.08–3.83, p=0.028)
・死亡またはESKD
発生:全体で27人(11.5%):standGC群 8人(7.4%)、redGC群 19人(15%)。
未補正:HR 2.09(p=0.08)
多変量補正後:HR 2.28(p=0.08)
IPTW補正後:HR 1.73(p=0.2)
・寛解前進行、再発、寛解達成
寛解前進行:IPTW補正後 HR 2.18(p=0.086)
再発(軽度+重度):IPTW補正後 HR 1.17(p=0.8)
寛解:IPTW補正後 HR 1.01(p>0.9)
・重篤感染(1年以内)
発生:18%:standGC群 16%(17人)、redGC群 21%(26人)(p=0.427)。
・サブグループ解析
redGC群内でクレアチニン>300 µmol/Lでは主要評価項目のリスク高(HR 3.02; 95%CI: 1.28–7.11)
RTX導入患者において、redGCは主要評価項目(aHR 2.36)、死亡またはESKD(aHR 3.45)リスク高
<Limitation>
・後ろ向き観察研究のため、適応交絡の可能性
・主要評価項目に複合アウトカム(死亡、ESKD、寛解前進行、再発)を設定したのは検出力を上げるためだが、アウトカムの性質が多様であること自体が限界
・患者の併存疾患に関するデータが欠如しており、死亡・ESKDリスクやGCレジメン選択の交絡因子としての影響を除外できない
・患者の約25%はメチルプレドニゾロンパルス療法を受けておらず、これもPEXIVASとの治療一貫性を損なう可能性
・standGC群ではGCレジメンにばらつきがあり、最短の追跡期間が6か月であった点から、長期評価に関しては慎重な解釈が必要。
・腎病理データが欠如しており、重度腎障害の背景に線維化変化など不可逆的な要因があるかは不明(PEXIVAS試験でも同様の限界)
・重症感染の頻度においてPEXIVASと本研究で傾向が異なるが、これは感染リスクが高いと見なされた患者にredGCが選択されやすかったという選択バイアスの可能性
・サブグループ解析は検出力不足の可能性
<研究の強み>
・PEXIVAS試験後、減量GC療法を検討した最初の報告
・PEXIVA試験は重症患者(重度腎障害or肺胞出血)のみをエントリーしているのに比して、より軽症な患者も含まれる点(1/4は腎臓、肺病変がいずれもない)
・RTX使用者の割合(PEXIVAS試験15%に対し本試験71%)が高い
・維持療法の違い(PEXIVASでは全例AZPに対し本研究では89%がRTX)
・血漿交換を受けた患者が少ない(PEXIVASでは50%に対し本研究17%)
・上記より日常臨床に即した実践的な患者集団での検討が実施できたこと
・本研究結果はLoVAS試験とも対照的だが、LoVAS試験は“6か月後の寛解”をアウトカムにしたものであるのに対し、本研究では再発や寛解達成前の進行、ESKD、死亡などに焦点をあてていることに意義がある。(LoVASは80%がMPAで重症者は除外)
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・GC減量レジメは症例を選ぶべきかもしれない。特にRTX使用例、Cr高値例において熟考すべき
担当:高橋良