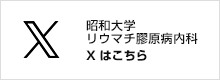Nerandomilast in Patients with Progressive Pulmonary Fibrosis: FIBRONEER-ILD Trial
進行性肺線維症患者におけるネランドミラスト 第3相試験
Toby M Maher, Shervin Assassi, Arata Azuma, Vincent Cottin, Anna-Maria Hoffmann-Vold, Michael Kreuter, Justin M Oldham, Luca Richeldi, Claudia Valenzuela, Marlies S Wijsenbeek, Emmanuelle Clerisme-Beaty, Carl Coeck, Hui Gu, Ivana Ritter, Arno Schlosser, Susanne Stowasser, Florian Voss, Gerrit Weimann, Donald F Zoz, Fernando J Martinez
Unità Operativa Complessa di Pneumologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome
N Engl J Med . 2025 Jun 12;392(22):2203-2214.
——————————————————-
<サマリー>
現在、原疾患を問わず進行性肺線維症(PPF)に対して承認されている抗線維化作用を示す薬剤はニンテタニブである。ネランドミラストは経口投与されるホスホジエステラーゼ4B(PDE4B)阻害薬であり抗線維化作用および免疫調整作用を示す薬剤である。今回、PPFに対する、ネランドミラストの有効性・安全性を検討するために行われた第3相試験である(FIBRONEER-ILD試験)。52週目におけるFVCの調整平均変化は、18mg群および9mgで有意に小さかった。
——————————————————-
P:18歳以上の進行性肺線維症患者
E:ネランドミラスト(18mg×2群、9mg×2群)
C:プラセボ
O:52週後のFVCの変化量
<セッティング>
・2022年11月16日〜2024年12月18日(52週)、日本を含む44カ国403施設
<研究デザインの型:RCT、横断研究、前向きコホートなど>
・二重盲検(患者、検者)、国際共同無作為化プラセボ対照比較試験
<Population、およびその定義>
・18歳以上、iPFを原疾患としない、ILD
・HRCTで病変が10%を超え%FVC≧45%・DLCO≧25%の患者であるが、経時的(2年以内)に%FVCの10%程度の低下もしくは5%程度の低下かつ臨床上呼吸状態の悪化/画像上の悪化を認める進行性肺線維症と認識する患者
・除外基準(Supplementary参照):閉塞性換気障害、直近で3ヶ月以内のAE歴/感染症歴/活動性のある膠原病、肝細胞障害/TBill上昇、腎機能障害(eGFR≦30)、肝硬変(Child≧A)、2年以内の自殺行為の既往/ Columbia-Suicide Severity Rating Scaleでtype4or5/ Hospital Anxiety and Depression Scaleサブスコア>14で定義されたうつ病、その他基礎疾患(高血圧,脳卒中,狭心症)、特定の肺病変の基礎疾患(COVID19後)、6週間以内の大手術、下記医療介入、妊娠計画
*免疫抑制剤の一定強度での使用:PSL15mg/日以上、IVCY、Tcz、MMF、RTX
*その他の治療:ピルフェニドン、その他のホスホジエステラーゼ阻害薬、幹細胞移植後
・実際の膠原病(Table.S1)は、全体の中で各群共にRA10%、SSc7%、MCTD4%、サルココイドーシス1%程度。
<主な要因、および、その定義>
・ネランドミラスト 18mgを1日2回内服群 (実使用量は36mg/日だが発表では18mg群と呼ぶ)
・ネランドミラスト 9mgを1日2回内服群 (実使用量は18mg/日だが発表では9mg群と呼ぶ)
<Control、および、その定義>
・プラセボ 1日2回の内服 錠剤の色・サイズ・形状を同一化
<主なアウトカム、および、その定義>
・主要アウトカム:52週目のFVC変化量
※スパイロメトリーは米国胸部学会/欧州呼吸器学会推奨のSpiroSphere(Clario)スパイロメータ
※PPFによる2年以内でのFVCの10%以上の低下は死亡率に関与する既報(PubID 32943410)
・副次アウトカム:急性増悪または死亡までの期間、呼吸器系疾患による入院または死亡までの期間、%FVCの10%以上の低下までの期間、%DLCO[Hb補正あり]の15%以上の低下までの期間、質問指標における呼吸困難スコア・咳スコア・疲労スコアの変化量
・有害事象の評価:よく知られる、2次性血管炎、うつ、自殺など
<交絡因子、および、その定義>
・年齢、性別、体重、喫煙、人種、使用薬剤の種類(ニンテタニブの有無)、HRCTパターン、試験前FVC、
<解析方法>
・3群にランダムに割り付け、ニンテタニブの使用の有無・HRCTパターンなど調整
・追跡期間:52週〜(最長130週)
・サンプルサイズの算出:図式的検定法を用いた一定の検出力担保を考えた際に、1群あたり347例とされた
・主要解析:反復測定データにおける混合モデル(MMRM)を用いた制限最尤法(REML)
・副次解析:Cox比例ハザードモデル、MMRMを用いたPEML
・欠測対処:52週以内に死亡した患者は最低値であるFVC10%低下に置換、それ以外の要因はランダムに欠損した仮説の元除外した
・3群間の多重比較を行い、αエラーの対策としてグラフィカル検定法を行なった
<結果>Figure1、Table1、Figure2、Figure3、Table2
・18mg群は391人、9mg群は393人、 プラセボ群は392人、の計1176人
・平均年齢は66.4歳(±10)、平均%FVC 70.1%(±15.8)、平均%DLCO 49.3%(±16.9) (±SD)
・各群の特徴(Table1)は、各群とも喫煙されたことない患者が約半数で、ILDの原因としては自己免疫疾患由来が約3割
・ニンテタニブ使用は各群約3割程度で、HRCTパターンは各群共約7割がUIPとして最多
・ベースとしての使用されていた免疫抑制・調整剤は、AZP、MTX、HCQ、Tac、CyA、IGU、コルヒチン、ABTなど(TableS4)
・主要アウトカム(Figure2):52週目におけるFVCの調整平均変化は、18mg群で−98.6 ml(95%信頼区間[CI]、−123.7~−73.4)、9mg群で−84.6 ml(95%CI、−109.6~−59.7)、プラセボ群で−165.8 ml(95%CI、−190.5~−141.0)
・18mg群とプラセボ群の調整後差は67.2 ml(95% CI, 31.9~102.5; P<0.001)
・9mg群とプラセボ群の調整後差は81.1 ml(95% CI, 46.0~116.3; P<0.001)
上記はニンテタニブの有無やHRCTのパターン別の解析においても同様の傾向
・副次アウトカム(Figure3):ILD の初回急性増悪、呼吸器系の原因による入院、または死亡は、18 mg 群で 95 例(24.3%)、9 mg 群で 110 例(28.0%)、プラセボ群で 122 例(31.1%)に発生
・プラセボ群と比較した、各ハザード比は、18 mg 群で 0.77(95% CI、0.59~1.01、P = 0.06)、9 mg 群で 0.88(95% CI、0.68~1.14、P = 0.34)
・有害事象(Table2)
・最も頻度の高い有害事象は下痢であり、18mg群の患者の36.6%、9mg群の患者の29.5%、プラセボ群の患者の24.7%に発現
・各群の患者のそれぞれ10.0%、8.1%、10.2%が有害事象のために中止
・治療中止に最も頻繁につながった有害事象は病状の悪化(すなわち、肺線維症の悪化)
・血管炎、うつ病、自殺念慮といった注目すべき有害事象に関しては、群間に差なし
<結果の解釈・メカニズム>
・PDE4B阻害薬は、細胞内cAMPを増加させ抗線維化および抗炎症作用を示すことにより(PubID 39183442)、進行性線維症患者の52週後のFVCの低下の抑制に寄与する可能性
<Limitation>
・特定のサブグループに絞った検出力不足
・自己免疫疾患患者によく併用されるミコフェノール酸モフェチルを内服している患者が除外
・観察期間内ではQOL関連の項目の改善は示されなかった
・臨床応用を考える際に、主な副作用が下痢であることから併用が予測される他剤と副作用内容がかぶる
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・薬理作用からは強皮症と相性が良さそうであり、強皮症単独やMMF併用下での追試などは気になる
<この論文の好ましい点>
・治療種が少ない抗線維化薬の新たな選択肢となりうる
文責:清水 国香