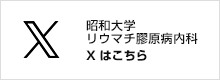乾癬性関節炎および軸性脊椎関節炎におけるTNFi中止後のサイクル対スワップ戦略
Cycle versus swap strategy after TNFi discontinuation in psoriatic arthritis and axial spondyloarthritis: a quasi-experimental study
Ilse van Es, Johanna E Vriezekolk, Nathan den Broeder, Lisan de Beijer, Alfons A den Broeder, Noortje van Herwaarden, Elien Mahler, Emmerik F A Leijten
Research, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, The Netherlands.
RMD Open 2025;11:e005566.
—————————————-
<サマリー>
PsAやaxSpAに対して最初のTNFiから薬剤を変更する場合、サイクル戦略とスワップ戦略の間での治療継続率はPsAでは同等、axSpAではサイクル戦略の方に優位性があった。
—————————————-
P:PsAおよびaxSpAで、最初のTNFiから薬剤変更を行った患者
E:サイクル戦略群(TNFi→別のTNFi)
C:スワップ戦略群(TNFi→IL-17i)
O: 3年後の治療継続率
副次評価項目として6か月、12か月、24か月時点での継続使用率
<わかっていること・わかっていないこと>
・乾癬性関節炎(PsA)や軸性脊椎関節炎(axSpA)の治療法は大幅に進歩し、特にb/tsDMARDsで新規の薬剤が次々に登場
・通常最初に使われるのはTNFiだが、PsA、axSpAともに1年間でのTNFi中止率が約30%であると報告されている。その後の選択肢として、別のTNFi、IL-17i、IL-12/23i、IL-23i、JAKiなど
・PsAやaxSpAで以下のどちらの戦略がより有効かについては判然としていない
・サイクル戦略:同じ作用機序の間で薬剤変更(TNFi→別のTNFi)
・スワップ戦略:新しい作用機序の薬剤に変更(TNFi→IL-17iなど)
・2つ目のTNFi継続は少なくともスワップ戦略と同等の効果があることを示唆するいくつかの研究あり
・RAのシステマティックレビューではスワップ戦略が有効であることを示すデータもあり
・研究目的:最初のTNFiを中止したPsAやaxSpA患者を対象として、サイクルorスワップの有効性比較、および有効性に関連する特性の検討
<研究デザイン>
・後ろ向き観察研究
<Population>
・オランダ、Sint Maartenskliniekで2012年から2023年3月までに治療を受けたPsAおよびaxSpAの患者のうち、
「最初のTNFiを中止、その後2番目のTNFiまたはIL-17iを処方され、2番目のbDMARDに関する6か月以上の追跡データ、あるいは6か月以内の中止に関する情報がある患者
・同病院では、プロトコルに基づき、2019年12月以前はサイクル戦略、以降はスワップ戦略(TNFi→IL-17i)を一般的な治療方針としていた(bDMARDs以前の治療経過や一次無効・二次無効は考慮せず)。
・筋骨格外症状などに配慮してプロトコルを逸脱することは許容
<主な要因、およびその定義>
・サイクル戦略:同じ作用機序の間で薬剤変更(TNFi→別のTNFi)
<コントロール>
・スワップ戦略:新しい作用機序の薬剤に変更(TNFi→IL-17iなど)
<その他データ>
・性別、年齢、罹病期間、BMI、axSpAのX線写真の状態、使用した薬剤および中止の理由
・疾患活動性パラメータ:
PsAの場合→DAS28-CRP、圧痛関節スコア(TJC)、腫脹関節スコア(SJC)
axSpAの場合→BASDAI
<アウトカム>
・主要評価項目:2番目のbDMARDに関する3年間の継続使用率
・副次評価項目:6か月、12か月、24か月時点での継続使用率
・治療中止理由:効果なし、副作用、寛解、計画妊娠、その他に分類
・データ抽出時に3年を経過しておらず患者がまだ治療を受けていた場合、また治療中止理由が寛解や計画妊娠であった場合はデータ打ち切り
<統計手法>
・PsAとaxSpAについては別々に解析を実施
・サイクル戦略グループとスワップ戦略グループのベースライン特性についてはSD、平均値、IQRで報告
・サブグループ(性別、最初のTNFiを中止した理由、一次無効かどうかで層別化)はStudentのt検定、Mann-Whitney U検定、カイ二乗検定で比較
・継続使用率についてはKaplan-Meierプロットを用いて視覚化
・交絡因子は多変量Cox回帰分析によって調整
<結果>
・患者特性
合計で406人のPsA患者と335人のaxSpA患者を対象
PsAではサイクル戦略307人vsスワップ戦略99人
axSpAではサイクル戦略270人vsスワップ戦略65人
ベースライン特性は、PsAでの最初のTNFiを中止した理由に差(無効が70.7%vs81.8%、副作用が26.4%vs16.3%)
・2番目bDMARDの中止
PsAでは258例で中止、191例(74.0%)で無効、67例(26.0%)で副作用
axSpAでは202例で中止、153例(75.7%)で無効、49例(24.3%)で副作用
・薬物継続率
PsAでは72.1%(6か月)、55.7%(12か月)、40.4%(36か月)
axSpAでは72.4%(6か月)、60.0%(12か月)、42.0%(36か月)
・サイクルvsスワップでの中止リスク
PsAでは、サイクルvsスワップで治療中止のリスクに有意差なし
層別化により、男性PsA患者ではスワップ戦略の方で治療中止リスクが有意に高い(HR 1.64(95%CI 1.03-2.60)、p=0.04)
axSpAでは、スワップ戦略の方で治療中止リスクが有意に高い(HR 1.46(95%CT 1.03-2.07)、p=0.04)
X線写真でaxSpAと診断された患者、最初のTNFiで一次無効であった患者でも同様の結果
2番目のbDMARDを開始した年(時期)が治療継続率におよぼす影響はなし。
・疾患活動性
疾患活動性の変化(ΔDAS28-CRP、BASDAI)については、サイクルvsスワップともに有意差なし。寛解、低疾患活動性達成にも有意差なし
<結果のまとめ>
・リアルワールドでの比較検討では、治療継続率や疾患活動性の面でスワップ戦略のサイクル戦略に対する優位性はみられず
・現在のガイドラインでの、同じ作用機序内でのサイクル戦略を推奨するという項目を裏付ける結果
<Limitation>
・SEKへのスイッチの時に導入用量ではなく通常量から開始のため、用量不足となった可能性(ただし、36か月にわたるフォローあり影響は少ない)
・治療時期の差によって臨床診療環境の変化があり、結果に影響を与えた可能性(ただし、時間的関連については検討しており、影響はみられない)
・後ろ向き研究であり不完全なデータ情報や交絡因子の影響
・昔のデータも使用しているため、PsA患者の皮膚疾患や腱付着部炎、axSpAのASDAS-CRPなどについては利用できず
・筋骨格外症状を伴うAS患者においては、この研究結果は当てはまらない可能性
<本研究の強み>
・臨床診療からのデータの使用→リアルワールドを反映した結果
・元々のbDMARDs変更プロトコルのため、割り付けのバイアスが抑えられた可能性
文責:井上良