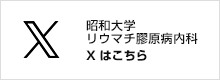Rituximab Versus Conventional Therapy for Remission Induction in Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis
EGPAに対する寛解導入療法におけるRTXは有効か?ROVAS Trial
Terrier B, Pugnet G, de Moreuil C, Bonnotte B, Benhamou Y, et al; French Vasculitis Study Group.
National Referral Center for Rare Systemic Autoimmune Diseases, Hôpital Cochin, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), and Université Paris Cité, Paris, France
Ann Intern Med. 2025 Jul 29. Online ahead of print.
——————————————————-
<サマリー>
EGPA寛解導入療法におけるRTXの効果と安全性を検討したRCT。RTX vs GCのみ or GC+IVCYにて寛解達成率は有意差なし(63.5% vs 60.4%)。各サブグループ解析(初発 vs 再発、重症 vs 非重症、ANCA陽性 vs ANCA陰性)でも差なし。
P:初発および再発のEGPA(BVAS3点以上)
I:RTX(1g2回)+GC
C:GC(重症例はIVCY併用)
O:寛解達成率
——————————————————-
<わかっていること>
・MPAとGPAに対するRTXの寛解導入療法の効果は、RITUXVASとRAVE studyにて示されている
・この2試験では、EGPAは除外
・2016年・2017年に2つの観察研究では、EGPAのRTX効果が示唆
・B細胞は、ANCA産生形質細胞の前駆細胞であり、かつ、T helper細胞に抗原を提示→これらによりEGPAの病態に関とするとの報告
<わかっていないこと>
・EGPAに対するRTXの寛解導入療法の効果のRCTでの検討はされていない
<今回の研究目的>
・RTXのEGPA寛解導入療法においる効果と安全性の検討
<セッティング>
・French Vasculitis Study Group networkに参加している施設
<研究デザインの型:RCT、横断研究、前向きコホートなど>
・RCT
・最小化法
・層別ランダム割付:初発/再発、重症(FFS1点以上)/非重症(FFS0点)、ANCA陽性/陰性
※薬剤介入ランダム化二重盲検の介入試験であり、RTXのEGPAに対する寛解導入の効果は検証は可能
※仮説としては、RTXが他のISより寛解導入達成率が高い
<Population、およびその定義>
・18歳以上の初発および再発のEGPA
・BVAS(ver3) 3点以上
・EGPA診断:1990ACRクライテリアを満たす、and/or、MIRRA trialの定義を満たす
※MIRRA trial 定義
BA既往か罹患中、好酸球増多(10%以上or1000/μl以上)、典型的なEGPAクライテリアの2つ以上を有する(好酸球性血管炎の組織学的証明、神経炎、肺浸潤影、副鼻腔異常、心筋障害、糸球体腎炎、肺胞出血、触知可能な紫斑ANVA陽性)、MPAかGPAと診断されていない
・除外基準:12ヶ月以内のRTX使用歴
<主な介入、および、その定義>
・RTX(1g点滴静注、day1及びday15に投与)
・グルココルチコイド(PSL1mg/kg)併用:ランダム化21日以内に投与開始
・重症例に対しては、mPSLパルス療法も可能
・維持療法
FFS0点:なし
FFS1点以上: 180日目からAZA(2mg/kg)
<Control、および、その定義>
・GC単独、重症例はIVCY併用
・IVCY使用時9回投与:1日目、15日目、29日目、50日目、71日目、92日目、113日目、134日目、155日目に投与
・維持療法
FFS0点:なし
FFS1点以上:180日目からAZA(2mg/kg)
<主なアウトカム、および、その定義>
・主要アウトカム:寛解達成率
・定義:BVAS0点+PSL7.5mg/日以下(180日時点において)
・副次アウトカム
・360日時点での寛解維持率:無作為化から360日後も寛解を維持している患者の割合
・完全寛解持続期間:BVAS=0かつPSL≤7.5mg/日を満たす累積週数
・再発フリー生存率
・プレドニゾロン使用量
・生活の質(QOL):Short Form-36
・機能障害:Health Assessment Questionnaire Disability Index score
・疾患後遺症:Vasculitis Damage Index
・有害事象:CTCAE version 3.0に基づく評価
・死亡
<解析方法>
・サンプルサイズ計算:寛解達成(RTX群85%、コントロール群60%)、10%drop、α=0.05人→108名と算出
・ITT解析の原則の則り解析
・主要アウトカムの解析:Multivariable log-binomial regression models
・調整因子:初発/再発、重症/非重症、ANCA陽性/陰性
・感度解析:追跡不能を除外して解析
・カプランマイヤー曲線・Cox marginal model:Cox marginal model
<結果>
研究対象者
・2016年12月~2019年10月に157名をスクリーニング
・52名除外後、105名が登録(リツキシマブ群52名、コントロール群53名)
・グルココルチコイド開始から無作為化まで平均9.27±6.89日
・102名(97%)が52週時点で研究完了
主要評価項目(180日での寛解率)
・RTX群:33名(63.5%)が寛解達成
・コントロール群:32名(60.4%)が寛解達成
相対リスク:1.05(95%CI: 0.78-1.42、 P=0.75)
副次評価項目
360日での寛解率
・RTX群:31名(59.6%)
・コントロール群:34名(64.2%)
相対リスク:0.93(95%CI: 0.69-1.26、 P=0.63)
寛解までの時間と持続期間
・寛解までの時間:両群とも中央値2週間
寛解持続期間
・RTX群48.5±6.51週、コントロール群49.1±7.42週(P=0.41)
再発フリー生存率
・RTX群:10名(19.2%)が再発
・コントロール群:10名(18.9%)が再発
HR:1.25(95%CI 0.5-3.11、P=0.63)
プレドニゾロン使用量
・研究期間中の平均累積用量:RTX群4591mg、コントロール群4453mg(両群間で有意差なし)
ANCA反応:MPO-ANCA陽性患者の360日でのANCA陰性化率
・RTX群:17/23名(74%)
・コントロール群:19/20名(95%)(P=0.100)
生活の質(QOL)
・SF-36身体:RTX群で6.98点改善、コントロール群で4.86点改善(P=0.47)
・SF-36精神:両群とも約1.6-1.8点改善(P=0.83)
機能障害
・Health Assessment Questionnaire:両群とも約0.3点改善(P=0.64)
疾患ダメージ
・Vasculitis Damage Index:RTX群0.31点増加、コントロール群0.14点増加(P=0.89)
安全性
・重篤な有害事象の発生率:両群で同程度
・最も多い重篤有害事象:感染症、次いで心血管イベント
・死亡:各群1名ずつ
・治療中止:6名(6%)、主な理由は有害事象4名、効果不十分2名
<結果の解釈・メカニズム>
・今回は優越試験としてデザインであり、非劣性試験ではないため、差がないとして捉えてはならない。
・本来RTXが用いられない非重症例(FFS0点)が60%を占めている群での結果であり、RTXを用いるであろう重症のセッティングのみを対象としたものではないことには注意が必要。今後の、この群を対象としたRCTが必要である。しかしながらサンプル収集が困難な可能性があり、実現可能性は不明。
・抗IL5抗体、抗IL5受容体抗体との寛解導入での比較検討は、今後必要であるエビデンスである。このRCTは現在進行中(NCT05030155)
<Limitation>
・研究デザイン:優越性試験の設計:非劣性試験ではなく優越性試験として設計されたため、重症患者におけるRTXとシクロホスファミドの同等性は評価は不可
・少ないサンプルサイズ:症例数が少なく、サブグループ解析の精度が不十分
・評価対象が限定:寛解導入に焦点を当てているため維持期での効果は不明
・追跡期間の不足:再発率の差異を検討するには、より長期間の追跡観察が必要
<結果と結論が乖離していないか?>
・乖離している
・「the results of this study showed that rituximab was not superior to the conventional five factor score–based strategy for induction therapy in patients with EGPA.」と結論部に記載があり、当初から非劣性試験であったように見える
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・EGPAに対するRTXの適応は、実臨床ではされつつあり、どのような群に用いるべきかが今後明らかになるであろう。
・現時点では、IVCY使用後の再発例、IVCY使用できない例、今後妊娠を考えている例、などに用いることが考えられる。
<この論文の好ましい点>
・論文の記載がとても丁寧
・研究の実施可能性を考えたうえでpopulationの絞り込まなかった事ことが想定されること
文責:矢嶋宣幸