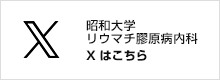Comparative effectiveness of subcutaneous sarilumab 200 mg biweekly, subcutaneous Tocilizumab 162 mg biweekly, and intravenous Tocilizumab 8 mg/kg every 4 weeks in patients with rheumatoid arthritis: a prospective cohort study
関節リウマチ患者におけるSAR200m every 2W sc とTCZ162mg every 2W sc、およびTCZ8mg/kg Div投与(4週間ごと)の有効性の比較:前向きコホート研究
Akira Onishi, Masao Tanaka, Takayuki Fujii, Koichi Murata, Kosaku Murakami, Motomu Hashimoto, Ryu Watanabe, Yuji Nozaki, Chisato Ashida, Wataru Yamamoto, Hirotaka Yamada, Sho Sendo, Kosuke Ebina,Hidehiko Makino, Yonsu Son, Yumiko Wada, Kenichiro Hata, Shuichi Matsuda, Akio Morinobu
Department of Advanced Medicine for Rheumatic Diseases, Kyoto University Graduate School
Arthritis Res Ther. 2025 Mar 7;27(1):52.
——————————————————————————–
<サマリー>
ANSWERコホート(RA多施設レジストリ)において、IL-6R阻害薬であるサリルマブ(SAR-sc群)とトシリズマブ(TCZ-sc群/iv群)の有効性を比較した。24週時点のCDAIの改善は、2W毎のSAR-sc群がTCZ-sc群と比較して統計的に有意に大きかった。TCZ-scとTCZ-iv群で差はなかった。また、48週の時点での薬剤継続率に3群で差はみとめられなかった。
P:ANSWERコホートにおけるIL-6阻害薬未治療RA患者
E:SAR-sc 200mg隔週
C:TCZ-sc 162mg隔週 と TCZ-iv 8mg/kg/回 月1回
O:24週時点のCDAI
——————————————————————————–
<わかっていること>
・SARとTCZはIL-6Rを標的とした異なる種類の抗体製剤
・SARは完全ヒト型でTCZは組換えヒト化の構造の違い、IL-6Rへの親和性(SARはTCZの20倍)やIL-6シグナル伝達阻害の効力(SARはTCZの約4倍の阻害)が異なる。
<わかっていないこと>
・実臨床でのTCZとSARの有効性の比較がない
<今回の研究目的>
・TCZ-sc 162mg隔週に対する:SAR-sc 200mg隔週および、TCZ-iv 8mg/kg/回 月1回の有効性の比較
<セッティング>
・縦断的多施設コホート研究である関西リウマチ性疾患患者の健康のためのコンソーシアム(ANSWER)コホート(2009年-2023年)
<研究デザインの型:RCT、横断研究、前向きコホートなど>
・ターゲット試験エニュミレーション:観察研究における理想的なランダム化比較試験を模倣する手法
・RA患者を無作為に割り付け、SAR-sc、TCZ-sc、またはTCZ-ivによる治療を非盲検下で開始する臨床試験を模倣する枠組みを用いた(3つの治療戦略を同時に比較)
<Population、およびその定義>
・対象集団はANSWER研究の全コホート。
・年齢が16歳以上、2010年ACR/EULAR分類基準基づき診断されたRA、IL-6Ri未治療患者
・日本で承認された開始用量および投与間隔で治療をうけている患者
・治療コース中の減量や投与間隔の延長といったステップダウン戦略は許容
・2カ月未満の一時的中止後の同薬剤の再導入は中止として記録しない
・除外基準:ベースラインで以前にIL-6Riを使用していた患者
<主な要因、および、その定義>
・SAR-sc 200mg隔週
・TCZ-iv 8mg/kg/回 月1回
<Control、および、その定義>
・TCZ-sc 162mg隔週
・2週間ごとに162 mgの用量で開始され、臨床反応に基づいて投与間隔は毎週に短縮
<主なアウトカム、および、その定義>
・主要評価項目:24週時点のCDAI
・副次評価項目:4、12、48週時点でのCDAI、24週と48週時点でのDAS28―ESR、48週時点での薬剤継続率と原因別継続率
・SDAIまたは血清CRP値をアウトカムとして用いた事後解析も実施
<解析方法>
・既存のシミュレーション研究でTCZsc(162mg隔週)の可溶性IL-6R占有率が84%(SAR-SC98%, TCZ-IV99%)と低いためTCZscとの比較
・逆確率重み付け(IPW)アプローチにより、治療群間のベースライン変数の差を考慮
・群間差は、連続変数については分散分析またはKruskal-Wallis検定、カテゴリ変数についてはFisherの正確検定を用いて分析。2群間の差は、標準化差に基づいて評価
・多重傾向スコアは、治療カテゴリーを従属変数とする多項式ロジスティック回帰を使用して推定
・TCZ-SCを比較対照として2つの一対比較をあらかじめ指定
・疾患活動性については、アウトカム解析はIPW差に基づき、ロバスト分散の線形混合効果モデルから95%信頼区間(CI)を算出
・反復測定には、非構造化共分散構造を持つ重み付き混合効果モデル
・維持率については、IPW調整Kaplan–Meier曲線を描き、ロバスト分散のCox比例ハザードモデルからIPWハザード比(HR)と95% CIを算出
・統計解析はRバージョン4.3.1(R Development Core Team、オーストリア、ウィーン)を用いて実施した。主要評価項目については、多重比較に対するBonferroni補正を適用し、統計的有意差はp<0.025
<結果>
Table.1 患者背景
・ANSWEコホートにけるRA12,248人の患者のうちIL-6Ri未治療患者1,001名(平均年齢61.5歳、女性81.6%)が研究基準を満たし、IL-6Riによる治療を開始した(SAR-SC群201名;TCZ-SC群546名;TCZ-IV群254名)
・SAR-SC群の特徴:他の2群と比較して、年齢が高く、罹病期間が最も短く、疾患活動性が最も高く、bDMARD/JAKiの未治療である可能性
・TCZ-SC群の特徴:女性である傾向があり、全治療群の中で最も低い疾患活動性
・毎週投与した患者は35名(6.4%)
・TCZ-IV群の特徴:罹病期間が最も長く、PSLおよびMTXの使用量が多く、以前に投与されていたbDMARDおよびJAKisの数が多い
Fig. 1
24週のCDAIの変化量
・SAR-sc群:−10.18(95% CI: −11.99~−8.36)
・TCZ-sc群:−7.64(−8.62~−6.67)
・TCZ-IV群:−6.64(−8.33~−4.95)
48週時点でのCDAIの変化量
・SAR-SC群では−11.16(95%信頼区間:−13.14~−9.18)
・TCZ-SC群では−8.40(−9.49~−7.31)
・TCZ-IV群では−8.39(−10.20~−6.58)
Table. 2 24週時点のCDAI変化量(主要評価項目)
・SAR-SC群でTCZ-SC群と比較して有意に低下(-2.53、95%信頼区間-4.38~-0.69、p=0.007)
・TCZ-IV群ではTCZ-SC群と有意差は認めず(1.00、95%信頼区間-0.68~2.69、p=0.243)
・4、12、48週時点でのCDAIの変化量について解析も同様の結果
・24週目と48週目のDAS28-ESRの変化量を副次評価項目として使用した解析でも同様の結果
・中等度から高度の疾患活動性患者に限定した解析でも、CDAI変化に関して同様の結果
・SDAIの変化量または評価項目として使用した事後解析でも同様の結果
Table.3/Figure.2 薬剤継続率
・交絡因子調整後、継続率は、TCZ-SC群と他の2郡に隔週投与群と有意差は認めず
・薬剤中止率を3群間で比較
・有効性不足による薬剤中止率は、交絡因子調整後、3群間で有意差は認めず
・TCZ-SC群と比較してTCZ-IV群有害事象による薬剤中止率が有意に高かった(HR: 2.51、95% CI: 1.45~4.34、p = 0.001)が、SAR-SC群群では差がなかった。
<結果の解釈・メカニズム>
・TCZ-IVからの切り替えはTCZ-SC隔週で十分である可能性がある。
・可溶性IL-6R占拠率の違いだけでなく膜型IL-6Rへの結合率なども影響しIL-6シグナル伝達阻害の違いがあるのかもしれない。
・中等度から高度の疾患活動性患者に限定した探索的解析では、SAR-SC 200 mg 2週間投与とTCZ-IV 8 mg/kg 月1回投与は、TCZ-SC 162 mg 2週間投与と比較して、低疾患活動性または寛解を達成した患者の割合に統計的に有意な差は認められなかった。
<Limitation>
・糖尿病や呼吸器疾患といった併存疾患は、疾患活動性よりもむしろ維持率の予後因子として主に機能していると考えられるにもかかわらず、本研究レジストリには併存疾患データが含まれていないため、3群間の交絡因子として調整されていない
・SAR-SC群は、他の2つの治療群の患者と比較して、疾患期間が最も短く、疾患活動性が最も高く、bDMARD/JAKi未治療である可能性が高いため、良好な臨床反応を示す傾向があったのかもしれない
・画像検査など評価していない
・治療中止の決定および中止理由が標準化された基準がなく医師の判断に依存
<結果と結論が乖離していないか?>
・乖離していない
・IL-6Rへの親和性からSARの効果が高いことを想定し、SARとTCZscの有効性を比較している
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・TCZからSARへのスイッチの有効性を示すものでないが、SAR緊急購入願い時の添付論文に使用可
・Fist IL-6RiとしてSARの優位性は考慮されるが今後、コスト面も考慮していく必要がある。
<この論文の好ましい点>
・多数の患者を対象とし、多施設共同で登録を行い、詳細な縦断的臨床データを前向きに収集したこと
・TCZとSARによる疾患活動性と薬剤維持率を実臨床で比較した初めての研究報告
・Primary outcomeである24週にくわえ48週まで同様の結果を得たこと。
文責:若林邦伸