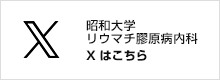Efficacy and safety of first-line biological DMARDs in rheumatoid arthritis patients with chronic kidney disease
CKD合併RA患者さんに対するfirstバイオの効果と安全性
Yoshimura Y, Yamanouchi M, Mizuno H, Ikuma D, Koizumi R, Kurihara S, Oba Y, Suwabe T, Sawada Y, Kamido H, Sugimoto H, Mizuta M, Sekine A, Hasegawa E, Ubara Y, Sawa N.
Nephrology Center and Department of Rheumatology, Toranomon Hospital Kajigaya, Kawasaki, Kanagawa, Japan.
Ann Rheum Dis. 2024 Sep 30;83(10):1278-1287.
——————————————————-
<サマリー>
CKDを伴うRA患者に対する第一選択のbDMRDsの効果と安全性の検討
とくにTNF-α阻害剤に比較しIL-6阻害薬の継続率が良い
——————————————————-
<わかっていること>
・CKDは、RA患者において一般人口より高い有病率
その要因:RAに伴うAAアミロイドーシス、、関節痛管理のためのNSAIDs使用、RA慢性炎症による動脈硬化や貧血の促進
・CKDを合併したRA患者治療の課題
▶感染症発症率が有意に高い
▶MTXはCKDによる使用制限
▶RAの不十分な管理は腎機能の悪化を誘発
▶NSAIDs使用による腎障害リスクへの注意
<わかっていないこと>
bDMARDsの有効性と安全性はCKD患者、特にHD例では十分に確立されていない
さらに、複数のbDMARDを対象とした包括的検討、長期追跡、十分な症例数による評価は行われていない
<今回の研究目的>
CKDを伴うRA患者に対する生物学的製剤ごとの継続率、有効性、中止理由を検討する
<セッティング>
期間:2004年1月-2021年12月
施設:虎ノ門病院、虎の門病院梶ヶ谷
<研究デザインの型>
後ろ向きコホート研究
<Population、およびその定義>
CKDを伴うRA患者
<主な要因、および、その定義>
・生物学的製剤使用(TNF-α、IL-6I、CTLA4-Ig)
・腎機能別に分類(eGFRが60以上、30~60、30未満mL/分/1.73m²)
・bDMARDsの投与方法(TNFαis、IL-6is、CTLA4-Ig)で分類。
・さらに、eGFRが<30 mL/min/1.73 m²の患者を非HDまたはHDに分類
<主なアウトカム、および、その定義>
・主要評価項目:第一選択薬としてのbDMARDの36ヶ月間の薬剤継続率
・副次的評価項目:DAS28-CRP、DAS28-ESR、およびPSL用量推移、ならびに中止理由の割合。
※中止理由は、リウマチ専門医によって4カテゴリーに分類:(1) 効果不十分、(2) 感染症、(3) 副作用、および(4) その他
<交絡因子、および、その定義>
年齢、CRP値、PSL用量、MTX用量(過去をもとに作成)
<解析方法>
・連続変数は中央値と四分位範囲で、分類変数は割合で基線特性を定量化。
・これらの特性を群間で比較し、連続変数についてはウィルコxon検定、クラスクアル・ウォリス検定、およびCuzickの傾向検定でp値を算出し、カテゴリ変数についてはχ2検定で比較。
・全体的な有効性と安全性の評価のため、上記カテゴリーにおけるbDMARDsの36ヶ月薬物継続率を比較。薬剤継続率の分析では、Kaplan-Meier解析により生存曲線を生成。
・Cox比例ハザード回帰モデルは、上記のカテゴリーに応じて層別化し、潜在的な交絡因子を調整して、第一選択bDMARDの中止に関するHRと95%信頼区間を推定。
・交絡因子は、年齢、CRP値、PSL用量、MTX用量(過去をもとに作成)
<結果>
■ベースライン:table1
各薬剤間のeGFRに差がある。MTX量、PSL量に差
CTLA4-Ig患者の罹病機関が短い
■bDMARDsの継続率(Figure 1A–D)
36ヶ月後の薬剤継続率:eGFR≥60、30–60、<30 mL/min/1.73 m²の3グループごとに記載
・すべてのbDMARDs:45.2%、32.0%、41.4%
・TNFα阻害薬: 45.3%、28.2%、34.0%
・IL-6阻害薬:47.4%、66.7%、71.4%
・CTLA4-Ig:42.9%、37.5%、33.3%
■eGFR<30の患者のbDMARDs継続率(Fig.2B)
・ 継続率:TNFα阻害薬(34.0%)、IL-6阻害薬(71.4%)、CTLA4-Ig(33.3%)
・TNFα vs IL-6 :HR0.27(95%CI 0.08~0.88、p=0.03)
年齢調整後HRは0.27(95% CI 0.08~0.88、p=0.03)
・TNFα vs CTLA4-Ig:粗HRは0.93(95% CI 0.28~3.07、p=0.91)
年齢とHD状態を調整後HR1.02(95% CI 0.29~3.61、p=0.97)
■薬剤中止理由(Table.2 )
・中止理由と全体的な傾向
第1選択bDMARDの中止理由で最も多かったのは「効果不十分」であり、すべてのサブグループで同様の傾向。
観察期間中に死亡例はなかった。
・腎機能(eGFR)と中止リスク
eGFR ≥60 群と比較し、eGFR <30 群での「効果不十分による中止」のハザード比(HR):粗HR 1.10(95% CI 0.89–1.37, p=0.38)、年齢調整HR 1.11(95% CI 0.89–1.39, p=0.35)。
eGFR ≥60 群と比較し、eGFR <30 群での「感染による中止」のHR:粗HR 1.20(95% CI 0.72–2.00, p=0.47)、年齢調整HR 1.20(95% CI 0.72–2.01, p=0.49)。
・薬剤種類別リスク(TNFα阻害薬 vs IL-6阻害薬, CTLA4-Ig)
TNFα阻害薬と比較した「効果不十分による中止」のHR
・IL-6阻害薬:粗HR 0.48(95% CI 0.21–1.08, p=0.08)、年齢調整HRも同値で有意差なし。
・CTLA4-Ig:粗HR 0.90(95% CI 0.50–1.64, p=0.74)、年齢調整HR 0.91(95% CI 0.50–1.65, p=0.75)。
TNFα阻害薬と比較した「感染による中止」のHR:
・IL-6阻害薬:粗HR 0.80(95% CI 0.19–3.40, p=0.76)、年齢調整HR同値。
・CTLA4-Ig:粗HR 1.63(95% CI 0.56–4.73, p=0.37)、年齢調整HR 1.58(95% CI 0.54–4.62, p=0.41)。
・HDの有無と中止リスク(eGFR <30群での解析)
非HD患者と比較したHD患者の「効果不十分による中止」のHR:粗HR 1.15(95% CI 0.53–2.50, p=0.73)、年齢調整HR 1.20(95% CI 0.51–2.83, p=0.68)。
非HD患者と比較した「感染による中止」のHR:粗HR 0.58(95% CI 0.10–3.46, p=0.55)、年齢調整HR 0.41(95% CI 0.06–2.89, p=0.37)。
・eGFR <30群における薬剤別解析
TNFα阻害薬と比較したIL-6阻害薬の「効果不十分による中止」のHR:粗HR 0.11(95% CI 0.02–0.85, p=0.03)→ 有意に低リスク。
TNFα阻害薬と比較した「感染による中止」のHR:粗HR 0.64(95% CI 0.07–5.79, p=0.69)、
<Limitation>
・サンプルサイズが小さい
・後ろ向き研究
・eGFR30-60mL/min/1.73mの患者群のIL-6使用者の少なさ
・CTLA-4-Ig患者のサンプル不足
・JAL阻害薬の除外
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・本邦の報告で、実臨床の実際の感覚に近い
・とくに感染症や心不全ふくめ動脈硬化性病態などの長期的なリスクはさらに長期的な観察が必要
・RCTなど、バイアスの少ないデザインも組まれるべき
<この論文の好ましい点>
比較的長い期間でサンプルを集めている点
実臨床で、結果的に重要である継続率をアウトカムにしている点。
文責:高橋 良