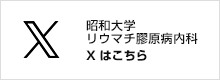Shorter reproductive time span and early menopause increase the risk of ACPA-negative inflammatory arthritis in postmenopausal women with clinically suspect arthralgia
臨床的に疑わしい関節痛(CSA)を有する閉経後⼥性において⽣殖可能年齢の短縮・早発閉経はACPA 陰性炎症性関節炎のリスクを上げる
Heutz JW, Boeren AMP, Claassen S, van Mulligen E, de Jong PHP, van der Helm-van Mil AHM
Department of Rheumatology, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands.
Rheumatology (Oxford). 2025 Aug 19:keaf438. doi: 10.1093/rheumatology/keaf438.
————————————————————————————————————
Summary;
Clinically Suspect Arthralgia (CSA)から炎症性関節炎(IA; Inflammatory arthritis)発症およびRA発症までの時間を、閉経前と閉経後の⼥性、および閉経後の⼥性において⽣涯のエストロゲン曝露期間によって⽐較し、またACPAの有無で層別化した。閉経後⼥性は閉経前⼥性と⽐較して、ACPA陰性IA・RAのリスクが⾼かった。早発閉経・⽣殖可能年数の減少・排卵年数の減少はACPA陰性IAのリスクを増加させた。
P:1年以内に⼩関節痛が発⽣したCSAを有する⼥性@オランダ
E:エストロゲン曝露期間が短い(閉経後、閉経後⼥性の中で⽣殖年数が短い、早期閉経)
C:エストロゲン曝露期間が⻑い(閉経前、閉経後⼥性の中で⽣殖年数が⻑い、正常/後期閉経)
O:IA/RAの発症率
———————————————————————————–—————————
<わかっていること>
・⼥性の更年期障害によるエストロゲンの減少は、⾃⼰炎症性疾患の発症・病勢に影響を及ぼす。更年期障害の時期は、関節リウマチの好発年齢(平均55歳)と⼀致している。
・実際に症例対照研究・前向き研究で、45歳以下で早期閉経した⼥性は正常/後期閉経の⼥性と⽐較し、RAの頻度が⾼いことがわかっている。
・⽣殖可能年数の短縮・エストロゲン累積曝露量の減少がRAのリスクを⾼めるとする研究もある。
<わかっていないこと>
・CSAからIA/RAへの進展における、閉経時期やエストロゲン曝露の影響は不明である。
<本研究の⽬的>
・閉経に関する因⼦がRAの病態⽣理に及ぼす影響を調べるため、CSAに注⽬し2つのコホートで縦断的研究を⾏った。
・閉経後の状態・⽣涯のエストロゲン曝露の短さがIA/RAの発症リスクと関連するかどうか、ACPA陽性/陰性とで異なるか検討した。
<Population、およびその定義>
・オランダの2つの独⽴したCSAコホート(ライデン、ロッテルダム)
・対象者数:コホート1(270名)、コホート2(163名)
・組み⼊れ基準
・発症1年未満の⼩関節痛
・リウマチ専⾨医がRAへの進展の可能性ありと判断
・ベースラインで臨床的関節炎なし
・除外基準
・ベースライン時に既に臨床的に関節炎が存在
・関節痛が他疾患で説明可能
・追跡
・追跡:2年間経過またはIA発症まで
・データ収集:4, 12, 24週、症状の増悪時には臨時でフォロー
・⾃⼰抗体:組み⼊れ時は不明(オランダのガイドラインでは推奨なし)
・ベースライン時の検査:⾝体診察、採⾎(ACPA(IgG)、カットオフ ≧7 U/mL)
・経⼝避妊薬やホルモン補充療法の使⽤に関する情報は得られず
<試験のデザイン>
・前向きコホート(2017年8⽉〜/2017年5⽉〜, 最⼤2年間追跡)
<主な要因、および、その定義>
・エストロゲン曝露
エストロゲン曝露に関連する3因子:生殖年数(閉経年齢-初経年齢)、排卵年数:(閉経年齢-初経年齢-(子どもの数×0.75年))、早期閉経(閉経年齢 ≤45歳)
取得方法:更年期関連の情報はベースライン時の質問票から取得。閉経と過去1年間の月経有無を確認
1年間無月経かつ閉経と回答した場合を閉経後と定義
<主なアウトカム、および、その定義>
・primary outcome:炎症性関節炎(IA)の発症
・secondary outcome:RAへの進展(2010または1987年分類基準を満たす)
<その他変数>
・治療の制限:DMARDs、GCは追跡終了まで許容せず
・IAの定義:リウマチ専⾨医診察で66関節のうちSJC≧1
・閉経の定義
ベースライン時に質問票で確認(「更年期であるか」「この1年で⽉経があったか」)し、
更年期と回答し1年間で⽉経がなかった患者を閉経と定義
・⽣殖可能年数:閉経年齢 – 初潮年齢
・排卵年数:(閉経年齢 – 初潮年齢)- ⼦どもの数×0.75(※妊娠期間9/12ヶ⽉)
・早発閉経:≦45歳(※)
<解析方法>
・閉経前と閉経後の⼥性のIA発症までの期間の⽐較のためCox⽐例ハザードモデルを使⽤
・解析はコホート1とコホート2とで別々に⾏った
・閉経後の⼥性は閉経前の⼥性よりも年齢が上となるため年齢で補正
・年齢が交絡因⼦として考えられるため、閉経前と閉経後の⼥性で別々に年齢がIA 発症と関連するか
検証した。男性CSA患者においても年齢がIA発症に影響するか検証した。
・P値≦0.05を統計的に有意とした
・STATA ver.18.0を使⽤
<結果>
・⼥性患者数:コホート1で211名(79%)、コホート2で163名(76%).
・年齢:両コホートで平均44歳.
・圧痛関節数:コホート1で中央値4、コホート2で中央値3.
・閉経している⼥性:コホート1で50名(⼥性の26 %)、コホート2で28名(⼥性の28%).
・両コホートの閉経後⼥性78名は、平均⽣殖可能年数36年、平均排卵年数は34年.
・閉経後⼥性全体のうち、23%で閉経年齢が早かった(45歳以下).
・閉経後⼥性は閉経前⼥性より⾼齢 (57歳 vs 38歳、P < 0.05).
・閉経後⼥性においてはACPA陽性が多かった(29% vs 10%、P<0.05).
・追跡期間:コホート1:24ヵ⽉[IQR:11-26]、コホート2:18ヵ⽉[IQR:8-24]
・IAの発症:コホート1:11%が発症、コホート2:18%が発症
・閉経前/閉経後の⽐較:
コホート1:閉経後でIAのリスク↑:22% vs 8%;HR 2.8 (95% CI 1.2-6.4)
コホート2:閉経後でIAのリスク↑:32% vs 13%;HR 2.6 (95%CI 1.01-6.4)
・ACPA陽性/陰性IA/RAと閉経後状態との関連
閉経後状態はACPA陰性IA/RAのリスク (HR 2.9, 95%CI: 1.1-8.0、HR 3.4, 95%CI: 0.5-24.2).
閉経後状態はACPA陽性IA/RAは有意に増やさず (HR 0.8, 95%CI: 0.4-1.9、HR 0.9, 95%CI: 0.4-2.1).
※IAを発症した患者のうち、70%が診断時にRAの定義を満たした.
・感度分析
閉経後⼥性は閉経前⼥性より⾼齢であったため、閉経状態を層別化した感度分析を⾏なった.
閉経前/閉経後いずれにおいても年齢はCSA→IAのリスクとは関連しなかった.
男性CSA患者でも年齢はIA発症の危険因⼦ではなかった.
→CSAからIAへの進展は年齢<閉経後状態が関連していると⽰唆.
・⽣殖可能年数・排卵年数とsn-IA
・⽣殖可能年数が1年増加する毎にACPA陰性IAのリスク低下と関連(HR 0.88、95%CI 0.78-0.99).
・排卵年数が1年増加する毎にACPA陰性IAのリスク低下と関連(HR 0.88、95%CI 0.78-0.99).
・早発閉経はACPA陰性IAのリスクを増加(HR 6.02、95%CI 1.34-27.10).
→閉経後CSA⼥性において、⽣涯のエストロゲンへの曝露が短いほどRAのリスクが⾼まる.
<メカニズムの説明(推測)>
・閉経後に炎症性サイトカインは増加がみられる.
・閉経後のエストロゲン⽋乏による炎症促進効果を⽰唆する.
・排卵前後など⾼濃度のエストロゲンはT細胞へは抗炎症作⽤を及ぼすが、B細胞活性は亢進し
⾃⼰抗体依存性疾患のリスクに影響すると推測される。
→閉経後にエストロゲンが不⾜するとT細胞制御が低下し、ACPA陰性RAのリスクが⾼まる?
・閉経前⼥性のエストロゲンは、卵巣から分泌される(17β-)エストラジオールが主であり、閉経後は
脂肪組織で産⽣されるエストロンである。
・エストロンのみ存在する状況のもとでは、RAの滑膜細胞はOA滑膜細胞と⽐較して炎症促進性の
エストロゲン代謝物の値が⾼い.
→滑膜内で単球増殖とTNF合成が阻害される?これが閉経後の⼥性の炎症性病態の説明となるかも?
<limitation>
・エストロゲン曝露期間として、⽣殖可能年数と排卵可能年数を⽤いたが間接的な測定
エストロゲン含有薬剤(経⼝避妊薬やホルモン補充療法など)の使⽤年数など、エストロゲン曝露に関するより詳細な情報が理想的には含まれるべき
特に更年期におけるホルモン補充療法の有無など。外因性エストロゲンの使⽤が結果に影響を及ぼした可能性
・更年期要因は質問票に基づいており、思い出しバイアスが⽣じる可能性
・早期閉経の定義は閉経年齢に関する質問に基づいており、⼥性⾃⾝の閉経年齢について認識が個々⼈で異なる可能性(特に1年前後のズレ)。
・CSAコホートから⼥性のみ(さらには閉経後⼥性のみ)を対象としておりnが少ない→年齢の交絡を排除するため閉経前・閉経後⼥性および男性において、年齢がIA発症と関連しないこと別途提示
・炎症性関節炎(Inflammatory arthritis)の定義が曖昧(1時点で1関節が腫れたら組み⼊れ)、CSAという概念⾃体もかなり不安定
・排卵前後のエストロゲンを「⾼濃度」と⾔っていいのか?妊娠期のエストロゲン量とは⽐にならない.(本当にそうならば⽉経周期により排卵前後は症状・炎症が緩和されるはず)
<本症例をどう活かすか>
・臨床的に疑わしい関節痛がある更年期⼥性では、ホルモン補充療法がIA/RAヘの進展を予防するかもしれない. 特にホルモン低下がある⾻粗鬆症ありなど.
・オランダにおける2つのコホートの結果であり、⽇本⼈に適応していいかは不明.
<本研究の強み>
・閉経後状態・エストロゲン曝露の短さがCSAのアットリスク群においてsnRAのリスクを⾼めたことを⽰した最初の研究
・2つの独⽴したCSAコホートを利⽤しており、閉経前⼥性と閉経後⼥性の⽐較に関する結果の妥当性を検証
・両コホートのデータを統合することで、エストロゲン曝露の⽣涯持続期間に関する解析において、閉経後⼥性のサンプル数を増やし統計的検出⼒を向上
・異なる閉経関連因⼦に対して⼀貫した結果
文責:道津 侑大