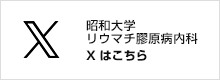Digital Psychological Intervention for Inflammatory Rheumatic Diseases
炎症性リウマチ性疾患(IRD)に対するデジタルツールを用いた心理介入
Johannes Knitza, MD, PhD, MHBA; Julia Kraus, MSc; Martin Krusche, MD; Isabell Haase, MD; Philipp Klemm, MD; Axel J. Hueber,MD, PhD; Alexander Pfeil,MD;Ulrich Drott, MD; Sebastian Kuhn, MD, MME; Jan Philipp Klein, MD
JAMA Network Open. 2025;8(9):e2529892
——————————————————-
<サマリー>
RAやSLE、PsA患者において自己主導型デジタル心理介入により、心理的苦痛や生活の質の改善につながった。
P:心理的苦痛があり日常生活の質の低下があるRA・PsA・SLE患者
E:デジタル心理介入
C:通常通りパンフレット配布
O: ベースラインから3ヶ月後の心理的苦痛(HADS-D)および生活の質(AQoL-8D)の変化
——————————————————-
<わかっていること>
・IRD患者の心理的サポートには、認知行動療法やアクセプタンス・コミットメント療法がしばしば使用
・これらの介入がIRDに伴う心理的苦痛の管理に有効であることは、研究によって一貫して実証
<わかっていないこと>
・IRD患者へのメンタルヘルス支援を推奨する強力なエビデンスと明確なガイドラインが存在
・しかしながら、サービス不足によりメンタルヘルス療法へのアクセスは制限され、待機時間が長期化
・その結果、IRD患者のかなりの割合が、自らの心理的苦痛を独自に対処せざるを得ない状況に
<今回の研究目的>
自己指導型ウェブベース認知行動療法介入であるVila RaVieがIRD患者の心理的苦痛軽減と生活の質向上に及ぼす有効性を評価する。・
<セッティング>
ドイツ全土でインターネット広告および患者団体・リウマチ専門医との連携で募集されたRAおよびPsA・SLE患者
<研究デザインの型:RCT、横断研究、前向きコホートなど>
・無作為化前向きコホート試験
・無作為化は2024年2月22日から6月4日にかけて、1:1の割付比率で行われた
<Population、およびその定義>
RA、PsA、SLE
選択基準:
・18歳以上であること
・インターネットアクセスを有すること
・有効なメールアドレスを提供すること
・ドイツ語を十分に理解できること
・書面によるインフォームドコンセントを提供すること
・心理的苦痛を示すこと(ドイツ語版病院不安抑うつ尺度[HADS-D]スコア≥スクリーニング質問票において、少なくとも1つのサブスケールで8点以上、および生活の質が低下(生活の質評価-8次元[AQoL-8D]スコア≤ 73.3%)
除外基準:(1)自殺リスク(2) 現在の心理療法歴(3) 過去6ヶ月以内の心理療法歴(4) 急性精神保健危機の既往(5)オンラインプログラムの自立使用を妨げる運動機能または認知機能障害(6) 過去6ヶ月以内のVila RaVieと類似したオンラインプログラムまたはアプリの利用(7) Vila Healthまたはnovineon CRO GmbHでの雇用(8) 研究者との意思疎通の困難、または研究者がプロトコル要件の遵守が困難と判断(9) 法的に判断能力の欠如(10) その他研究者の判断で研究実施に支障をきたす要因を有する
<主な要因、および、その定義>
通常治療を継続するとともに、デジタル心理介入へのアクセスを提供
<Control、および、その定義>
一般的なリーフレットのみ受け取り、説明
<主なアウトカム、および、その定義>
・主要評価項目:ベースラインから3ヶ月後の心理的苦痛(HADS-D)および生活の質(AQoL-8D)の変化
・副次的アウトカム:自己効力感、健康リテラシー、知覚ストレス、機能障害、抑うつ、不安の変化
<解析方法>
・サンプルの計算はG効果量0.50(予想脱落率20%を含む)、検出力0.80、α=0.10を仮定した場合、標本サイズは102名と算出
・感度分析として、主要アウトカムをPer-protocol集団)および完遂者集団で再解析
・薬剤変更の有無(あり vs なし)および年齢(65歳未満 vs65歳以上)に基づくサブグループ解析を実施
・ベースラインから治療中間期および治療終了時までの変化量は、治療群、訪問回数、治療群×訪問回数交互作用、ベースライン値、疾患状態を固定効果とする反復線形混合効果モデルを用いて解析
・患者内誤差のモデリングには制限付き最尤推定法と非構造共分散構造を採用
・推論統計にはケンワード・ロジャー近似法を適用
・各治療群間のベースラインからの変化量における最小二乗平均(標準誤差)差と、対応するCohen dが効果量推定値として用いた
・レスポンダー解析として、HADS-Dでは5.7(44)、AQoL-8Dでは0.06(45)を最小臨床的意義差(MCID)と定義し、臨床的に意味のある改善を達成した患者の割合を算出
<結果>
・スクリーニング対象372名中、102名(平均[標準偏差]年齢47.2[12.9]歳;女性92名[90.2%]、男性10名[9.8%])
・平均[標準偏差]疾患期間は8.4[9.0]年であった。102名の参加者のうち、37名(36.3%)がRA、33名(32.4%)がPsA、32名(31.4%)がSLE
・介入群では、HADS-D総スコアの平均値(標準偏差)が、ベースライン時の19.60(5.30)から治療後には13.35(5.99)に減少した。対照群ではベースライン時20.42(5.70)から治療後17.36(6.81)への減少が認められた。介入群では対照群と比較して、HADS-DのMCID(最小臨床的意義のある最小評価量)を達成した参加者の数が有意に多かった(29名[59.2%]対17名[34.0%];オッズ比(OR)、2.81;95%信頼区間(CI)、1.24-6.37;P = .02)
・介入群では、AQoL-8Dスコアの平均値(標準偏差)がベースライン時の0.62(0.11)から治療後0.69(0.13)に上昇した。対照群ではベースライン時0.62(0.11)から治療後0.65(0.14)への上昇であった。これにより介入群のスコア上昇幅が有意に大きいことが示された( 最小二乗平均[標準誤差]差:0.04[0.02];P = .047;Cohen d = 0.49)。MCIDを達成した参加者の割合は、介入群で有意に高かった(27名[55.1%]対 16名 [32.0%]; オッズ比(OR)2.61; 95%信頼区間(CI)1.15-5.91; P = .03))
・機能障害を除く二次アウトカム指標でも同様の改善パターンが認められた。介入に関連する有害事象は報告されなかった
<結果の解釈・メカニズム>
・心理的苦痛の大幅な軽減は主要評価項目と副次的評価項目の双方で一貫して観察され、介入群において臨床的に有意な改善を達成した参加者の割合が有意に高かった。
・追加解析では、特に65歳未満の患者および乾癬性関節炎患者において、抑うつよりも不安に対する効果が強いことが明らかになった
・疼痛や患者総合評価には有意な効果が認められなかった
・仕事と社会適応尺度への効果が見られなかったことは、心理的症状の改善が日常生活機能の向上に完全には結びついていない可能性を示唆している。
<Limitation>
・サンプルサイズが小規模であった。
・男性が少なかった。
・層別無作為化が行われておらず、ベースラインに偏りが見られた。
・参加者は主に自己選択であり、デジタルリテラシーが高い傾向にあったため、募集プロセスで選択バイアスが生じた可能性がある。
・長期的な効果を評価するための長期追跡調査が実施されなかった点も限界である。心理療法を受けている参加者や自殺念慮の兆候がある参加者を除外したこと、および低関与対照群を用いたことは、効果サイズを過大評価し、一般化可能性制限した可能性がある。
[考えたLimitation]
・スクリーニング対象患者のうちスクリーニング中止となった患者が多い印象(スクリーニング中止となった理由が見つからなかった)→これは一般的か?
・介入群にRAが、対照群にSLEが多い印象
<結果と結論が乖離していないか?>
結果と結論は解離していないように思われる。
<どのように臨床に活かす?どのように今後の研究に活かす?>
・例えば専門医の少ないような地域でIRD患者の心理的負担を軽減する一つの手段として、デジタル心理的介入ができるのではないか
・ただデジタルリテラシーの低い患者の場合や高齢患者においてどのように介入すべきかは今後の課題であろう。
<この論文の好ましい点>
・心理療法用有害事象質問票(NEQ)と自由記述式質問(電話フォローアップを含む)を用いた有害事象の体系的かつ継続的な評価
・SLEやPsAを含む免疫介在性リウマチ性疾患患者向けに特別に設計されたデジタル心理的介入の効果を評価した初の研究である。
文責:河森 一毅